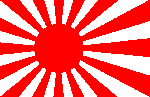
|
| ★ 目 次 ★ |
| ☆ 人生の原風景 |
| ☆ 先祖先達に学ぶ |
| ☆ 世の中は役割分担 |
| ☆ 『大和ごころ』 |
| ☆ 教育は家庭から |
| ☆ 『國體の本義』 |
| ☆ 「修身書」の活用 |
| ☆ ARNKAメール報 (拉致関連@チェンマイ) |
| ☆ AVの愉しみ |
| ☆ 管理人の日記 |
| ☆ クロ仲間放送局 |
| ☆ 海外旅行記 |
| ☆ 掲示板(bbs) |
当サイトへのお問い合わせ先↓
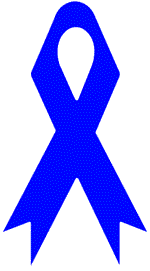
| ★ 世の中は役割分担 ★ |
| ★ 日本人の感性(1) |
| 古来、日本人は、森羅万象の「無常」(無情ではない)に気づき、「人生のはかなさ」を知りました。他者に対しても、同じ運命を背負う人間仲間として捉え、深く共感できたのです。そこから、「思いやり」「いたわり」という優れた感情を表出しました。無常とは、万物は生滅流転して永遠不滅のものはない、とする元来の仏教用語です。 祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。 娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。 おごれる人も久しからず、唯春の夜の夢のごとし。 たけき者も遂にはほろびぬ、偏に風の前の塵に同じ。 「平家物語」の劈頭文です。無常観を見事に表現しています。いかに権勢を振るって栄耀栄華を極めようとも、多くの権勢なき人々と同じように、やがて死んでいきます。未来永劫、盛者であり続けることなどできません。無常を知ればこそ、敗者や弱者の姿に、明日のわが身を見る思いがして、敗者への思いやりとか弱者へのいたわりといった感情が湧き上がるのです。人間の本能的な反応を別にすれば、これは日本人だけが持ち得る感性です。ドライな欧米はもちろん、アジア他国にもみられません。 「思いやり」「いたわり」は、世界が羨む日本人の感性です。 |
| ★ 日本人の感性(2) |
| 日本人が持つ感性の他なる特徴は、より繊細で敏感で多様な点です。太陽を見て、「真っ赤な」「灼熱の」「ジリジリと照りつける」「ギラギラした」「燃える」といった形容詞をつけるのは、日本人ぐらいのものでしょう。唯物的な西洋人なら、感受性が研ぎ澄まされた詩人でもない限り、太陽は太陽でしかありません。 秋の夜長を鳴き通す虫の声を聞いて、詩情を感じるのも日本人です。しかも、こおろぎ、松虫、鈴虫などの鳴き声を聞き分けているところが凄い。他国の人々にとっては、どれも単なる雑音にしか聞こえていないのです。 フランスでは、日本の漫画(劇画)がブームになっているそうです。当たり前ですが、日本語は仏語に翻訳されます。ところが、多種多様な「擬音」が出てくるので、翻訳者は頭を抱え込んでいるといいます。 仏語のことはよく知りませんが、「擬音」ぐらいはあるでしょう。犬のワンワン、にわとりのコケコッコー‥‥etc.。そうしたどこにでもある音ではないのです。花が「パッ」と咲く、「ピューピュー」風が吹くなど、普通なら音を感じない場面で「擬音」が出てきてしまいます。究極は、物音一つしない状況を「シーン」などと表現します。音のない「擬音」なんてフランス人には理解できません。 自然界を豊かな感性で捉える日本人は、世界に誇る詩人です。 |
| ★ 「武士道」の価値観 |
| 武士(=侍)はその文字が示すとおり、もともと高貴な人に侍り(付き添う)、その身辺警護が仕事でした。役目柄、要人より華美な振る舞いは許されず、常に死を覚悟していなければなりませんでした。このことが質実剛健な精神構造を生み出し、支配階級となったあとも、「武士道」として武家社会の規範になっていきます。明治維新で武士階級はなくなりましたが、代わって徴兵制が採用されたため、武家だけの「武士道」からむしろ一般庶民にも拡がり、大東亜戦争に敗れるまで、日本人の精神的支柱であり続けました。 武士道における価値観は、西洋的なそれとは対極をなします。 ・新しいものよりも古いもの ・華美よりも質素 ・物質的な豊かさよりも精神的な豊かさ ・私利よりも公利(滅私奉公) ・動よりも静 ・剛よりも柔‥‥etc. そして彼らは、自分の命より名誉のほうを重んじました。それに増してすばらしいのは、「惻隠」(かわいそうに思うこと。あわれみ)に高い価値を見出していたことです。弱い者いじめや敗者に鞭打つなどの卑怯を最大の恥とし、弱者敗者をいたわり、護ってやるのが武士の情けでした。 戦後、アメリカ的価値観を妄信する人が増え、武士道精神は急速に忘れ去られようとしています。軍国主義と結びつけて、頭ごなしに非難する人もいます。しかし、卑怯者がはびこる現代社会にあって、かつての凛とした日本を取り戻すためには、遺伝子に組み込まれているはずの「武士道」を蘇らせるしかありません。 |
| ★ 何のために生きるか |
| 昔の子供向けチャンバラ(伝奇物)映画には、一つの共通した流れがありました。まだ子供だった時分には、主役を自分にダブらせて、興奮しながら観ていたので、気づきませんでしたが‥‥。 1.主人公は、山賊ら悪党に乗っ取られた領主の忘れ形見。 2.成長してその事実を知る。 3.忠義な家臣が、ほかに隠れ住んでいることがわかる。 4.家臣たちと結束して、ついに悪党一味を滅ぼし、お家を再興する。 大ざっぱに言って、こんなあらすじです。そして、狼藉の限りを尽くす悪党の逆襲をうけて、窮地に立つ主人公側の場面が、必ず出てきます。それが主人公であれば、家臣が代わって斬られます。女子供であれば、母親が身代わりになって自分の命を捧げます。襲われた姫君は、「寄らば、わらわが喉を突く(自決する)。」と抵抗します。悪党一味に、命を投げ出すほどの人物はいません。一味のなかにも、悔い改めようとする者が現れますが、時すでに遅く、裏切り者として大概が斬り捨てられてしまいます。 映画に限らず、当時の子供向け雑誌・漫画本・小説・ラジオ・テレビなどは、すべてといってよいほど、こうした物語の展開で貫かれていました。単純な勧善懲悪だけではなく、「何のために生きるか」を示唆していたように思います。 つまり、この世界に登場する正義の人は、みんな「命より大切なもの」を持って生きています。悪党にはそれがないから、卑怯者の醜態をさらすことしかできないのです。家臣なら主君に、母親なら子供に、姫君なら貞操に、自分が護るべき対象を見出しています。それは生き甲斐の一つであり、「何のために生きるか」という自分が果たすべき役割の自覚に他なりません。 |
| ★ 自分の役割を知る |
| 自分は、何を為し何のために生きるのか。前章では、人間一人の存在が弱くて小さいことを学びました。だから、社会(組織・世の中)という共同体を作って、お互いが助け合って生きていかなければならなかったのです。 社会構成をみると、家族があって、地域があって、市町村があって、都道府県があって、地方があって、はじめて国家があります。社会の最小単位は、家族です。親と子、夫婦、兄弟姉妹との付き合い方が、まさに社会と関わる基本です。親は子をいつくしみ、子は親に孝行を尽くし、夫婦は仲むつまじく、兄弟姉妹は仲良くしなければなりません。これが、それぞれの立場での接し方です。そうです、立場によって自分が為すべき役割は変わります。会社も、上司・部下・同僚を親・子・兄弟にみたてれば、自ずと関わり方が見えてきます。地域や国家に対しても同様です。 世の中は、役割分担の仕組みになっています。独り暮らしをすればよくわかることですが、家の中では自分がすべてをしなければなりません。掃除をしなかったら、ゴミの山です。掃除のできない人は、ゴミが出ないよう工夫するしかありません。世の中の仕組みも同じです。自分のことは自分でする。これが原則ですが、すべてができる超人なんていません。自分にできない部分は、他人に助けてもらっているのです。裏を返せば、自分には苦もなくできることでも、それができない他人もいるということです。 自分に何ができて何ができないか、を知ることが先決です。自分にできないことをしてくれる人々に感謝しつつ、自分にできることで他人(世の中)を助けてあげることが、人生に課せられた使命ではないでしょうか。できないことを力ずくでやらせようとしても、通用しません。独裁者や悪党の常套手段です。社会にしてもらいたい(要求)ことよりも、自分が社会にしてあげられる(貢献)ことを考える方が、はるかに大切です。人間の評価とは、そういうものだと思います。 |
2006年2月14日更新
